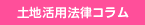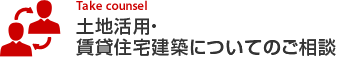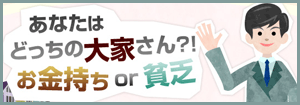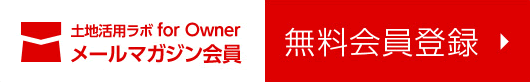事例(7): 店舗の賃貸借契約を締結していたが、テナント店舗から賃料の減額請求をされた
この事例は、建物を所有する方が店舗として利用する目的で賃貸していたところ、賃借人から賃料の減額を請求されたというケースです。今回のケースでは、当事者間の協議が整わず、簡易裁判所での調停も不調に終わったので、賃借人から賃料減額請求訴訟が提起されたのでした。
賃料の増減を請求することは可能
借地借家法32条1項本文は、現行の賃料が経済事情の変動や近隣の建物の賃料と比較して不相当になったときは、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができると規定しています。長期間にわたることが多い不動産賃貸借契約において、契約当初の事情から変動があって賃料が不相当になった場合にまで、当初の賃料で当事者を拘束するのは当事者間の衡平を害し、酷だと考えられるからです。賃料の増減額については、まず、当事者間の協議によって決めます。当事者間の協議が整わないときは原則として簡易裁判所に民事調停の申し立てを行います(調停前置主義)。民事調停が不調に終わった場合には、賃料減額請求訴訟を提起して、裁判所が相当賃料を決めることになります。
【相当賃料の算定方法】
相当賃料を算定するには不動産鑑定士の鑑定によることが多いのですが、算定方式は、積算方式、スライド方式、賃貸事例比較方式、差額配分方式、総合方式といった方式があります。各方式の内容についての説明は紙面の都合上割愛しますが、建物賃料については裁判例でもどの方式によるか確たるものはありません。
【賃貸人の対応】
賃貸人が減額賃料に同意しない場合でも、賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、自ら相当と考える賃料を請求することができます(借地借家法32条3項本文)。
もっとも、裁判が確定した場合において、既に支払いを受けた賃料の額が正当とされた賃料の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息をつけて返還する必要がありますので注意が必要です(同項但書)。
【賃料を減額しない旨の特約は有効か?】
では、賃借人から減額請求されないように、賃貸借契約で賃借人から減額請求できない旨の特約をつけておくのはどうでしょうか?
この点については、借地借家法32条1項は、当事者間の特約によって排除的な強行規定と考えられているので、このような特約は無効です(最判平成16年6月29日判時1868号52頁)。
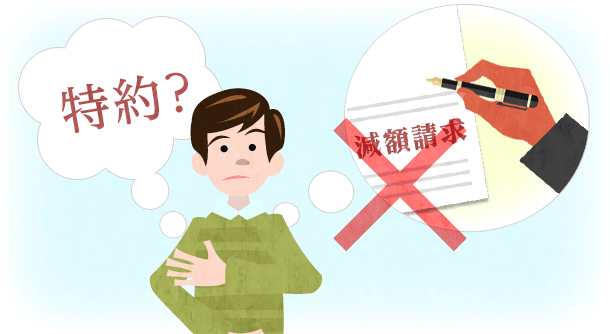
事例(8): 土地を貸したけど、景気の変動や周辺環境の開発もあり、賃料の増額を請求したい
事例(7)とは逆に、賃貸人側から賃料の増額を請求したケースです。
増額請求に同意できない賃借人は、自ら相当と考える賃料を支払えばよいのですが、事例(7)の賃貸人と同様、裁判で増額賃料が確定した場合には不足額に年1割の利息をつけて支払う必要があります(借地借家法32条2項但書)。また、賃借人の方が増額前の賃料を支払おうとしても賃貸人が受領を拒絶した場合に、賃借人が賃料を法務局に供託することがあります。
今回のケースは、賃貸人の賃料増額請求に対して賃借人が増額前の賃料を10年間、法務局に供託を続けた事例です。
このような事例で、賃貸人は増額を請求した10年前から増額した賃料を請求できるのでしょうか。
賃料の増額請求権
事例(7)でご説明したとおり、賃貸人も、経済事情の変動や近隣の建物の賃料と比較して不相当になったときは、契約の条件に関わらず、賃料の増額を請求することができます。
賃料の増額請求権(減額請求権)を行使すれば、その意思表示が相手方に到達した時点で、相手の承諾がなくても将来に向かって相当額に増額(減額)されます(このような権利を「形成権」といいます)。そのため、消滅時効の起算点は、裁判で正当な賃料の判断が確定したときからではなく、所定の弁済期から進行することになります。
また、賃料請求権は、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する(民法169条)」となっています。
そのため、所定の弁済期から5年を経過した時期の増額賃料については賃借人が消滅時効を援用した場合には、増額請求することができなくなりますので注意が必要です。