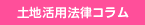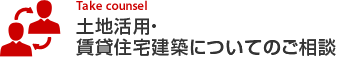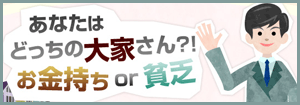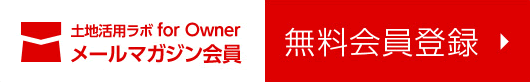コラム vol.058
(第4回)司法書士が語る
「不動産取引と成年後見制度についての基礎知識」
執筆:司法書士 星野大記
公開日:2014/12/10
我が国では高齢化の進展とともに、認知症の人数も増加しています。65歳以上の高齢者では平成22年の時点で、7人に1人程度、約15%とされています。
そして、最近の不動産取引実務においても、認知症の疑いがある方の不動産の売買の相談が増えています。
法律の基本に立ち返りますと、不動産の売買取引には、本人の「意思表示」が必要です。
では仮に売主が認知症の疑いがある場合、意思表示があるのかないのか、どのように判断するべきでしょうか?
例えば、次の事例ではどうなるか一緒に考えてみましょう。この点、認知症は意識障害+記憶障害+判断力障害によるものですが、ご本人の症状のレベルによって法的な判断能力があるかないかを判断する必要があります。
そこで、実務的によく利用されているものは「長谷川式簡易知能評価スケール」という30点満点の10~15分くらいのテストを行うものです。名前、年齢、居場所、日付などから簡単な記憶問題、引き算の計算問題などが内容で、21点以上を判断能力ありと判定します。
では、判断能力がないと判定した場合はどのような手続きが必要となるでしょうか?
その場合は、成年後見制度を利用することになります。
判断能力のレベルによって3段階となっていて、最も重いのが「後見」、次に「保佐」、そして「補助」といい、本人、配偶者、4親等内の親族等による家庭裁判所への申立により審議され、審判により後見等が開始します。
仮に最も重い「後見」が必要と審判された場合、認知症の方を成年被後見人、その代理人となる方を成年後見人といいます。
成年後見人には親族が選任される場合もありますが、適切な候補者がいない場合は司法書士などの専門家が選任されることになります。
成年後見人は成年被後見人の代理人として、本人のための様々な法律行為を代理して行なう、本人にとって代わるものすごく強い権限を有することになります。
成年被後見人の不動産を購入する場合、売買価格や契約内容の取り決め、その他売主側の手続きも全て、成年後見人が代理して行なうことになります。
成年後見人が強い権限をもっているため、親族による後見、情けないながら専門家による後見であっても、横領する事件が増加しており、平成24年には、全国で575件(内9割が親族後見)、被害総額は約46億円となり、ともに統計開始以来の最多を記録しています。
また、特に専門家による成年後見人は本人にとっては赤の他人で、認知症発症前の本人のことを全く知らない場合が殆どであり、本人の好きな食べ物や趣味なども知らないような人が自分の財産の処分権限を包括的に代理させることになるわけですから、「本人のため」になるか否かの判断は法的に厳格になり、融通を利かせられる範囲も限定的にならざるを得ません。
そこでご紹介したいのが、「任意後見制度」です。
任意後見制度とは、本人が元気なうちに、認知症、交通事故、脳疾患などにより意思能力が低下する場合に備えて、自分自身が信頼できる方(法人でも可)を任意後見人として任意後見契約を締結しておくものです。
任意後見契約の内容は、法定の成年後見人とは異なり、かなり柔軟に内容を決めておけるので、万一認知症が発症した場合であっても、本人のことを知っている方が本人の好きな食べ物や趣味などのためや、好きな場所に連れて行ったりするために出費することができます。また不動産の購入や売却についても、その条件面や相手の選定方法などを決めておいたりすることもでき、非常に有用です。
不動産を用いた相続税納税対策や節税対策が必要となる不動産オーナーにとっては、相続対策の一環として利用を検討すべき制度だと思われます。