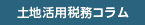コラム vol.446
コラム vol.446令和5年度税制改正
資産課税に関する改正について
公開日:2023/03/29
POINT!
・令和5年度の税制改正により、暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長される
・相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わり、2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税が課税されない
・相続は人によって異なるため、専門家に相談するのが良い
令和4年12月23日に令和5年度の税制改正大綱が閣議決定されました。その中でも、不動産オーナーの方々にも大きくかかわる、相続税や贈与税といった資産税関係の改正内容についてご紹介します。
元来、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっていました。そのため、相続税がかからない方、相続税がかかる方であっても多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっていました。
ただし、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適用されていました。つまり、相続税がかからない方々にとっては、贈与税を支払ってまで贈与することを選択する人は少ないため、資産家の方に有利な税制になっていたともいえます。
国としては、ご高齢の方々が所有する財産を早期に若い層に渡していくために、相続税がかからない方々にとっても、贈与がしやすいように改正をする必要がありました。
図1:相続税と贈与税の関係

令和5年2月財務省資料より
暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長
資産の大きさによる不公平さや生前贈与しにくい状況を改善するために、令和5年度税制改正では、暦年課税制度における生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年に変更されました。
暦年課税制度では、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すこととなっていました。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になるというものです。
暦年課税とは
贈与税額は、年ごとに贈与を受けた財産の合計額を基に計算されますが、110万円の基礎控除を超える部分が贈与税の対象となり、110万円までの贈与は課税されません。生前贈与により、相続時の財産を減らすことができますが、贈与者の死亡前3年以内の贈与財産は相続税の計算に含まれます。これが生前贈与加算です。贈与財産110万円の基礎控除以下の贈与についても、死亡前3年以内であれば加算対象となりますが、加算の対象となるのは相続人と遺言などで財産を取得した人だけです。
この「3年」という期間は、諸外国と比較すると非常に短いため、諸外国にならって3年から7年に延長されました。適用時期は、2024年(令和6年)の1月1日以降に贈与した取得財産に関する相続税から適用されます。
亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じです。しかし、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算する必要があります。
2027年(令和9年)の1月1日以降、加算される年数が伸びる
2024年1月31日に亡くなった場合、生前贈与加算の対象となる贈与は、2021年1月31日~2024年1月31日の3年間の贈与です。ですから、2017年1月31日~2021年1月30日の贈与は税制改正前の贈与ですので、対象になりません。2027年以降から、加算される年数が3年より長くなります。
ただし、2027年(令和9年)の1月1日以降、いきなり7年間に延ばしてしまうと、法律と実態が合わなくなることから、2027年(令和9年)から2031年(令和13年)まで持ち戻しの期間が、3年から4年5年6年7年と1年ずつ増やす形で計算されます。年が進むにつれて徐々に加算される年月が長くなり、2031年1月以降の相続から、まるまる7年加算されるようになります。
たとえば、相続人である子ども2人に毎年110万円贈与を行ってきた人が亡くなり、相続開始日が2027年(令和9年)6月1日になったとします。
その場合は持ち戻しの期間が4年になります。
現行では3年間の持ち戻し期間として660万円が持ち戻しとなりますが、加えて令和6年の1月1日の金額も持ち戻しの対象となります。
図2:生前贈与加算の金額 具体例

ただし、相続開始前3年から7年の贈与については、贈与の相手1人100万円は控除できることになっていますので、この220万円から100万円×子ども2人分、計200万円を差し引いた20万円をプラスして生前贈与の加算額を決定します。つまりこの場合、660万円プラス20万円の680万円が生前贈与の加算となります。
相続時精算課税制度の改正
もう1つ、「相続時精算課税制度」が大きく変わるのも、令和5年度税制改正の大きな点です。
相続時精算課税とは、2,500万円の特別控除額までは贈与税がかからず(特別控除額を超えた場合は一律20%の税率で贈与税がかかります)、贈与を受けることができるものの、贈与者が亡くなったときに贈与でもらったものもすべて相続財産に加えて計算されるという制度です。そのため、生前贈与により相続時の財産を減らすことはできません。
多くの方は暦年贈与を使って贈与を行われますが、この相続時精算課税制度を選択することも可能です。
2024年の贈与から年110万円までなら贈与税が課税されない
今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。 2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税が課税されません。
図3:相続時精算課税制度の見直し 改正内容

これまでも、暦年贈与については、毎年110万円までは贈与税の控除として基礎控除がありましたが、相続時精算課税制度を選択すると、その110万円の基礎控除というのが適用できませんでした。
今回の改正によって、110万円の基礎控除ができるようになりました。またこれまでは、相続時精算課税制度を使うと、すべての贈与が相続税の対象になっていましたが、年間110万円のこの基礎控除の金額は相続税の対象から外すことができるようになりました。つまり、金額が安い贈与であれば相続時精算課税を使った方が、税額が安くなるわけです。
図4:相続時精算課税制度の見直し 改正前後の比較表

改正前と改正後の計算方法を比較してみます。
改正前の内容ですと、贈与額から2500万円を差し引き、20%の贈与税を申告納税する必要がありました。2500万円までは贈与税がかからず、贈与することができます。
2500万円を超えた部分についても、相続時に精算課税をしますので、相続時にその贈与した金額を合わせて相続税の計算をします。支払った贈与税はその相続税から差し引くことができますので、結論として贈与税というのはかかっていない形になります。これが相続時精算課税制度です。
この相続時精算課税制度は、すべての財産が相続税の対象になりますので、一度、相続時精算課税制度を使うと、それ以降の贈与はすべて相続税の対象になってしまいます。
通常、贈与というのは相続税が減ることを前提に使うことが多いため、この相続時精算課税制度を選択してしまうと、すべて相続税の対象になってしまいますので、あまり使われることはありませんでした。使われるケースとしては、相続財産に加算する贈与財産の評価額は、贈与時の評価額で行う必要がありますので、現在の評価額で相続税の評価をしておく必要があります。例えば将来値上がりが期待されているような資産であれば、今100の評価で贈与できて、将来1000になることが予測されるのであれば、評価額が低いうちに相続時精算課税制度を選択し、贈与をしておくことによって、相続税の対象の評価額を低く抑えることができます。将来収益をもたらすもの、あとは値上がりするもの、そういったものはこの相続時精算課税制度を使うことが今でも行われております。
また、将来、資産価値が上がることを予測した相続という意味では、これまで、相続時精算課税制度は、事業承継対策として使われるケースがありました。オーナー経営者が自社株を時価の低いときに贈与すれば、相続時に株価が上昇していたとしても、贈与時の価値で計算されるため、将来かかる予定の相続税を抑えることができます。
これまでは少額の贈与であっても申告が必要であり、手続き面での負担がありましたので、相続時精算課税制度の利用件数はそれほど多くありませんでした。しかし、110万円までであれば贈与税も相続税もかからず、申告も不要となれば、利用者側のメリットは大きくなります。
高齢者から若年層への早期の資産移転は、日本の経済にとっても大きな課題です。高齢化が進むなか、日本銀行の「資金循環統計」によれば、家計金融資産は60歳以上が約6割を所有しているとされており、高齢者が持つ資産を若年層へ移転させることで、消費や投資を促し、ひいては日本経済を活性化させることにつながることが期待されます。
暦年贈与と相続時精算課税の使い分けをどうするか
ここまで紹介した、暦年課税制度と相続時精算課税制度ですが、どのような方がどちらを選択すれば税制上、有利に働くのでしょうか。
まだまだお元気で、相続まで生前贈与の持ち戻し期間7年よりもまだ時間があるという方は、これまで通り年110万円までなら非課税になる暦年贈与の基礎控除を活用して、時間をかけて次世代に資産を移転させるのが良いでしょう。
また、相続人や受遺者ではない人は、生前贈与加算は適用されない点を活用すれば、孫や甥(姪)のために、暦年課税制度を活用するのが良いかもしれません。
一方、余命わずかなご高齢の方が『子に生活資金を少しでも前渡ししたい』とお考えの場合は、相続時精算課税制度が良いかもしれません。
亡くなる直前であっても年110万円までなら、贈与税が課税されません。
前述の事業承継においても、株価の低い時点で贈与したうえで、110万円の控除枠を活用しながら、事業資金の贈与を行うケースが考えられます。
いずれにおいても、相続は人によってすべて異なり、同じケースは2つとしてありません。複雑な計算が必要なケースもありますので、公認会計士や税理士などの専門家へ相談されることをお勧めします。
監修:税理士法人朝日中央綜合事務所 公認会計士・税理士 小平康弘