



「DXで建設業界を変えていく」
大和ハウス工業のDXが新たなフェーズに突入した。施工現場に導入されたDXが社員の働き方を変え、
日本の建設業界をも変えていく。
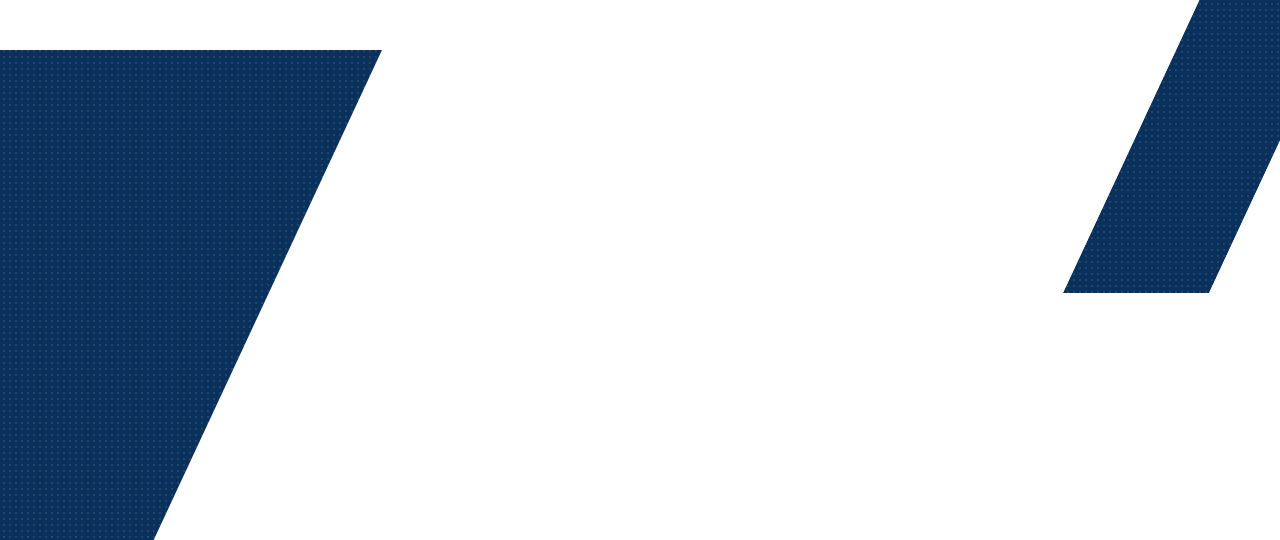


![]()

![]()
![]()
![]()
![]()



建設業界の課題をDXで解決する
都市には次々と新しい風景が生まれる。施工現場の現場監督として指揮を執る照﨑も、多忙な日々を過ごす。ここ数年は関東を中心にホテルの施工を担当。今はJR山手線の近くにある商業施設の現場にいた。
朝礼では、デジタルサイネージを使って作業内容や注意事項を共有する。これまで情報を伝える手段は紙や口頭での指示だったが、アナログからデジタルへと移行した。デジタルサイネージは、大和ハウス工業が急ピッチで進める「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」の一端だ。
建設業界、特に施工現場は今、大きな課題に直面している。人手不足や2024年問題といわれる時間外労働の上限規制、そしてデジタル化やリモートワークが進む社会から周回遅れで取り残されたアナログなワークフローなどが挙げられる。
施工現場を中心で支えるのは経験豊富な施工店の職方たちで50代、60代が多い。彼らのような熟練工が引退すれば、匠の技で乗り越えてきた現場も滞る可能性が高くなる。幸い大和ハウス工業は協力会社に恵まれ、人手を確保できているが、今後はそうもいかなくなる気配が濃厚だ。去年の夏は型枠大工が手配できず、ようやく沖縄から来てもらうこともあったそうだ。
時間外労働の上限規制は、大和ハウス工業だけでなく建設業界全体がどう対処すべきか頭を悩ませている。原因の一つは、工事部門の業務タスクがとんでもなく多い点にある。照﨑がある現場で作成した図面などのデータを数えたところ、その数は約40万にものぼった。その上、「建築系施工管理の業務量を正確に把握するのは、雲の量を把握するのと同じぐらい難しい」と言う。手掛ける建物の多くは、製造業やシステム建築と違ってオーダーメイドのため、着工後、設計変更がたびたび起こる。刻一刻と変わる状況に対応していかなければならず、自分で仕事の時間配分や量を決めづらい点も原因の一つだと考えている。
2019年、照﨑はBIM※推進プロジェクトにDX率先者として加わることになり、後に率先垂範する者として建築系DXリーダーに任命される。2017年からBIMが推進されてきた設計部門に続き、施工部門でも取り組みが始まったのだ。
「そもそも施工現場のDXって何だろう?何から手を付ける?」
招集された数名のDX率先者とDX推進部メンバーで集まってみたものの、誰も正解がわからない。まずは現場で行われる業務にデジタルツールを用いるなど、さまざまな試行を繰り返すうちに一つのことが見えてきた。
当初は「BIM=3次元CAD」だと思っていたが、活動開始から約1年が過ぎた頃から、BIMはデジタルデータを蓄積し、それらを活用することで業務を効率化する画期的なワークフローだということに照﨑も気付き始めた。「BIMは大きな中心軸で、BIMに絡むアプリケーションやIoT測器、ICT建機が連動することで、さらなる業務の効率化が図れる」と感じている。
※Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の略称。3次元の建物のデジタルモデルにさまざまな属性情報を追加し、あらゆる工程で情報を活用する画期的なワークフロー。

タブレットで現場の進捗や工程などを管理

デジタルサイネージで情報共有



アメリカからD’sBIM※を世界へ発信
DX率先者としての活動が始まって約1年後の2020年9月、大和ハウス工業とAutodesk社はBIMやDXをさらに加速させる目的で、戦略的連携に関する覚書を交わした。Autodesk社のスタッフは、照﨑たちの固定概念を次々とぶち壊した。「できない」と思っていたことを、「なぜできないんですか?」と疑問を投げかけてきたのだ。
例えば、従来設計への質疑はメールや電話、直接会うなどして情報を得、手書きで図面に書き込んでいた。Autodesk社は「それはエビデンスとして蓄積されますか?後々分析できますか?」と問う。当然できないし、必要性を感じていたが対処法を探すという発想に至らなかった。
しかし、「できない」ままでは進化はない。まずはAutodesk社のソフトウエアを活用し、PDFに質疑や回答期限をテキストで打ち込み、全ての質疑には「その質疑に至った原因」など、タグを付けて分類するようにした。そうすることで、電話1本30秒で済んでいた従来の方法よりも時間はかかるが、工事業務を圧迫している原因を見つけ出し、蓄積して分析できるようになり、数年後には負担が一気に減るだろう。
Autodesk社との協働が軌道に乗った頃、米国で毎年開催されるグローバルイベント「AU(Autodesk University)」の存在を知る。建築、製造、メディア&エンターテインメントなど各業界をけん引するイノベーターや企業が世界中から集まり、最先端の技術や取り組みを披露し、学び合う。期間中に開催されるカンファレンスは450セッションを超え、2022年は約1万人が会場へ足を運び、約3万人がオンラインで視聴した。
照﨑は「セッションの登壇者として参加したい」と手を挙げた。大規模なグローバルイベントだ。英語での発表には準備にも時間を要する。しかしながらD’sBIMの取り組みを社内で広めるには、日本だけではなく海外も含めた対外的な評価が必要だと考えたのだ。世界中から応募された企画提案書の中から当社の案は第三者機関の審査を通過し、2022年9月、アメリカ・ニューオーリンズへ。経営者や本社部門の登壇者が多い中、照﨑たちはヘルメットと作業服姿で講演に挑む。現場の人間が現場で本当に必要としているDXを報告するセッションは、参加者に大きなインパクトをもたらし、質疑や意見交換が多数あった。
講演成功の高揚感に包まれ帰国した照﨑たちだったが、残念ながら、その成果は社内でほとんど注目されていなかった。BIMなどのデジタル技術改革は、主に設計部門を中心に進められており、工事でのデジタル改革はまだまだ知名度が低いので当然である。現場で働く社員は多くの業務タスクに追われて多忙を極め、新しい情報をキャッチアップする余裕が持てない。照﨑自身も、過去のAUに自社が参加していたことを知らなかった。だからこそ「社内の反響が低いのは想定内」と語る。
「しかし、今後さらに建設DXが普及する時代が必ず訪れます。その時、世界的なイベントで自社の取り組みが早くから評価された事実は、きっと私たちの自信につながります」と、これからの活動にも意欲を示す。
※D’sBIM:大和ハウス工業が手掛ける全物件をBIM化し、業務の効率化を進めるプロジェクト。

照﨑たちのセッションの様子



新しい仕事のポジションをつくる
コロナ禍でリモートワークが広がってきた頃、1人の社員が照﨑のもとに配属された。結婚を控えていて、パートナーになる人は群馬で勤め暮らしているという。彼女は「本当はこのまま東京工事部で働きたい。大きな建物の施工に携わることは、大学時代からの夢なんです」と悩んでいた。
一緒に働き始めると、彼女は非常に優秀だった。「現場工務」と呼ばれる事務所内の業務、例えばお施主さまや施工店とのやりとり、定例会議などのレジュメ作成、施工図の管理などに秀でた才能があったのだ。
建設DXの流れに乗せれば、リモートワークで彼女の能力を活かせるのではないか、と照﨑は考えた。全社的にリモートワークが広がってはいるものの工事部での前例はまだない。「群馬に住んでいても『東京工事部』の一員としてできることは十分にある。その体制を共に整えよう」と可能性の追求を約束した。
何度も工事部のトップや人事部との交渉を重ねた結果、新しい働き方のモデルケースとして正式に群馬からリモートワークで現場工務を行えるようになった。後日、彼女が産休に入る時、「群馬に引っ越して辞めることになると思っていたのに『ずっと働き続けたい』『産休が明けたらまた戻ってきたい』と思える環境を作ってくれて本当にうれしかったです」と言ってくれた。
さらに東京工事部には、照﨑が長年必要だと言い続けてきた「生産技術グループ」も発足した。フロントローディング班は、着工前に図面の不整合などをチェックし、設計担当者や設備担当者へのフィードフォワード業務を担当。施工図班は、着工前から着工後も現場の施工図の作図を担当する。生産技術グループも現場工務と同様にリモートワークでの業務が可能なため、さらに可能性は広がった。特定の業務を担うひとりの負荷が上がることを当たり前とせず、その負担を分散させる。かつ個々の能力を発揮しながら生産性を高めていく。そんな理想をかなえる場所が徐々に実現し始めた。
全国の事業所にも、さまざまな事情で悩んでいる人がいるだろう。制度や組織を変えるのは簡単なことではないが、確実に変化は始まっている。照﨑も、フレックスタイム制が導入されてから時々子どもを保育園に送れるようになったという。他の父親たちが子どもを送迎する姿を見て、「なぜ自分たちにはできないのだろう」と疑問に思っていたのも過去の話だ。世の中の変化、そしてDXの勢いは止まらない。この新しい働き方も必ず全国へ広がっていく、と確信している。

新たに発足した生産技術グループ



DXは必ず私たちを楽にしてくれる
照﨑は「施工現場がDXに取り組まないことは、会社にとっても自分にとってもイメージできなかった。取り組まないことはリスクでしかない」と感じていた。そう思ったきっかけは、アメリカにあるグループ会社Daiwa House Construction Management Inc.の社長から聞いた話にあった。
契約社会のアメリカでは、建設業界の契約も非常に透明性が高い。お客さまの都合で何かを変えることになった場合、その要望が契約範囲外であれば解決が見いだせるまで必ず工事はストップするという。日本では、ゼネコンが融通を利かせるよう求められ、工期も、支払われるお金も変わらないことが多い。社長が「アメリカの文化を日本に広めたい。このままでは日本の建設業界は良くならない」と語った言葉に、照﨑は目の覚める思いがした。
危機感は他にもある。「日本の建設業界が海外の建設会社と戦うためにもDXを進めなくては」と焦りが募る。他の業界では、懸念はすでに現実だ。また、企業としてだけでなく、個人としてDXリテラシーを高めることも生き残りにつながる。DXを理解して活用できる人と、そうでない人とでは、生産性に圧倒的な違いが生まれる、と照﨑は断言する。
照﨑をDXへと駆り立てる根底には、工事に携わる人たちを“楽”にしたいという強い思いがあった。「工事は、何事もなく無事に竣工して100点。でも、天候など自分たちにはどうにもできない理由で予定が遅れたり、アクシデントが起こって減点される可能性が非常に高い。だから必死に仕事をこなして100点を目指すことに注力する」と憂う。「休みの日に街を歩いていると、他社の施工現場は土日も昼夜も関係なく、みんなが汗をかいて働いている。こんな状況で、建設は魅力的な仕事だと思われ続けるだろうか」と気にかける。
施工現場のDXが進めば、大和ハウス工業だけでなく、建設業界全体が変わっていく。現場で働く人たちに時間や気持ちのゆとりが生まれ、視野が広がれば、もっとみんなのためになるアイデアが出てくるに違いない。さまざまなチャレンジが良しとされれば、120点の現場も実現するかもしれない。建設業界の可能性は無限大だ。
「私は、建設が好きで、施工管理の仕事が好きなんです。だから『工事担当者で良かった』『工事担当者になりたい』と思ってくれる人を増やしたい」と照﨑は夢を語る。建設DXなら、施工管理を、いや建設という仕事を、もっと魅力的なものに変えられる。照﨑が見る未来はどこまでも広く、明るい光に満ちている。
※掲載の情報は2023年7月時点のものです。





















