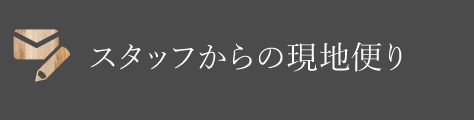120年のめざめから現代に蘇る「薩摩切子」
日本にキリスト教の布教のためフランシスコ・ザビエルが来日した
1549年(天文18年)に、ヨーロッパからガラス製品が伝わってきたと
云われます。
かつて日本では、ガラスのことを“びいどろ”と呼んでいました。
ポルトガル語のガラスを意味する“ヴィドロ”が、なまった言葉だそうです。
中世ヨーロッパから隆盛を極めていたガラス工芸品は、
江戸時代に入り
長崎出島を通じて輸入されていました。
当時、伝わった主なガラス製品は
イタリアのヴェネツィアングラスや
チェコのボヘミアグラスなど といった大変高価な代物でした。
 幕末期の日本にも・・・
幕末期の日本にも・・・
ガラス製品の本場であったヨーロッパに勝るとも劣らない、
ガラス工芸品「薩摩切子」が
誕生していました。
薩摩のガラス製造の発祥は
1846年(弘化3年)
薩摩藩27代当主、
島津 斉興(しまづ なりおき)公の
藩主時代に始まりました。
1851年、
後の28代藩主、
島津 斉彬(しまづ なりあきら)公が
「薩摩切子」を世に送り出しました。
それを完成させるまでの道のりは、決して容易ではありませんでした。
研究と試行錯誤を繰り返し、長い年月を経て、
薩摩はようやく切子の完成に至りました。
1855年、
日本最初の洋式産業群“集成館事業”を推し進めていた
斉彬(なりあきら)公は、製鉄、造船、紡績などと共に硝子方を設け、
本格的な「薩摩切子」の製造が始まったのです。
1858年(安政5年)には、
長崎海軍訓練生と共に薩摩藩を訪れたオランダの軍医も
ガラス工場を見学した折、
100人以上がそこで働いていたなどと克明に記しています。
斉彬公が昇華させた「薩摩切子」は大変に先進的な工芸品で
自らもこれを愛用し、諸国の大名へ贈り物に用いました。
またNHKのドラマにもなった篤姫が、
嫁入り道具のひとつとして、
徳川家に献上されたゆかりの工芸品でもありました。
しかし、
斉彬公が急逝した後の1863年(文久3年)、
薩英戦争で集成館は英国海軍の砲撃を受け、
これによりガラス工場は壊滅的な被害を受けました。
そして、その後存続は図られつつも
1877年、「薩摩切子」は途絶えてしまったのです。
 一度は歴史に幕を閉じた
一度は歴史に幕を閉じた
「薩摩切子」でしたが昭和60年、
薩摩藩主の末裔である島津興業に
より復元事業が始まります。
腕利きのガラス職人たちと
志を持った若者達が
各地から集められました。

そして120年ぶりに 「薩摩切子」
「薩摩切子」 を復活
を復活 させたのです。
させたのです。
この時の復活事業に参加した若者の一人が
弟子丸(でしまる)努さんでした。



更に挑戦は続きます。
これまでの「薩摩切子」は
紅、黄、緑、藍などの伝統色が中心に
作られていました。
切子師の弟子丸さんは、
平成18年、不可能と言われていた
黒色のガラス生地に、カット細工を施す
今までにない
「薩摩黒切子」を産み出しました。
一般的に切子は、溝の幅や断面の形状に違いを持たせるため、
生地の硝子をライトの透かしを頼りに、高速で回転する様々な形状の
ダイヤモンドホイールでガラスを削ります。
一方、黒切子にいたっては、
黒生地の硝子を透かしても何も見えません。
まるで、暗闇の中で手の感覚だけで切る行為。
まさに、熟練の技が必要とされるのです。




弟子丸さんは切子師として修行を続け、
6年前に故郷の霧島市国分でガラス工房弟子丸を開き、
「薩摩切子」の伝統を引き継ぎながら後継者の育成も行っています。
「薩摩切子」の魅力は、手に取った瞬間ズシリと重く、
手に溶け込むような滑らかな手触りと光沢があり、
ほかのガラス製品にはない不思議な魅力に惹きつけられます。
 弟子丸さんは、
弟子丸さんは、
オリジナルブランド「霧島切子」も
作製しています。
『薩摩切子の基本を守りつつ、
もっと自由な発想で霧島切子を
世界に広げたい』と
弟子丸さんは熱い想いを語って
くれました。
工房の敷地内にある店舗には、
食器や花器以外にも指輪やブレスレッド、イヤリング、タイピン
更にはステンドグラスなど、様々な切子の作品が並びます。
これらの作品を見ていると、
固定概念に囚われない世界観が広がり、
それは伝統の中に新たな価値が吹きこまれているようでした。
時代ごと移り変わっていくラフスタイルに合わせ、
伝統工芸品も変わっていく必要があるのかもしれません。
これから、
どんな「薩摩切子」が登場してくるか楽しみです。

美の匠 ガラス工房 弟子丸
霧島市国分清水1-19-27
TEL 0995-73-6522
※ロイヤルシティ霧島妙見台より約9㎞
※写真はすべて平成29年2月撮影